本記事は、SDGs(持続可能な開発目標)の中でも特に注目される「SDGs14」について、小学生向けにわかりやすく解説します。
「海の豊かさを守ろう」という目標は、私たちの日常生活と深く結びついており、誰もが取り組める大切な課題です。
海洋プラスチックごみの問題や、ゴミ拾い活動の意義、家庭や学校でできる具体的な行動まで、「私たちにできること」をたっぷり紹介します。

SDGsについて知りたい方や、小学生にも伝わるシンプルで実践的な内容になっていますのでこれを機にあなたも「海の豊かさを守る」行動を始めてみませんか?
- SDGs14「海の豊かさを守ろう」の内容がわかる
- 海洋ごみ問題などの課題を理解できる
- 小学生向けの具体的な行動例が学べる
- 私たちにもできることが明確になる
【小学生向け】SDGsとSDGs目標14とは?わかりやすく解説
SDGsとはなんの略?小学生向けにわかりやすく解説
まずは、SDGs(エスディージーズ)という言葉の意味をわかりやすく簡単に説明します。
SDGsは「Sustainable Development Goals」の略で、日本語では「持続可能な開発目標」と言います。
これは、地球上のすべての人々が安全で健康に暮らし続けられるよう、2030年までに達成すべき17の目標と169の具体的なターゲットから成り立っています。
この言葉が登場した背景には、地球の環境問題や貧困、紛争、感染症など、私たちの生活に大きく影響を与える課題が存在しています。
これらの課題を解決しないと、将来的に私たちが地球で安全に暮らせなくなってしまう可能性があります。
そのため、世界中の国々が協力して、これらの問題に取り組むための目標を立てたのです。
SDGsは、地球の未来を守るためのナビゲーションのような役割を果たしており、私たち一人ひとりが何をすべきかを示してくれます。
小学生の皆さんも、この目標について知ることで、自分たちがどんな行動をとるべきかを考えるきっかけにしてほしいと思います。
なぜSDGsが重要なのか?地球の未来を守る目標
SDGsが重要な理由は、人類が直面する多くの課題を解決し、持続可能な社会を築くための行動計画だからです。
地球上では、自然環境の破壊や資源の枯渇、経済格差が進んでいます。
これらは放置しておくと、私たちや次の世代の暮らしを大きく脅かすものになります。

例えば、海洋汚染が進むと魚や海洋生物が減少し、私たちの食生活や仕事に影響を及ぼします。
また、気候変動が進むことで自然災害が増え、生活環境が厳しくなることも懸念されています。
このような問題を未然に防ぐため、SDGsの17の目標が設定されました。
具体的には、「貧困をなくそう」「教育をみんなに」「海の豊かさを守ろう」などの目標があります。
それぞれの目標がつながっており、一つの課題を解決することで他の問題にも良い影響を与えるように設計されています。
そのため、SDGsは地球全体を良くするためのバランスの取れた行動指針と言えるのです。
SDGsの17の目標とは?全体像を解説
SDGsの17の目標は、私たちの暮らしや未来に関わる幅広いテーマを網羅しています。
以下はその主な内容です。
-
貧困をなくそう:すべての人が最低限の生活を送れるようにする。
-
飢餓をゼロに:誰もが十分な食べ物を得られるようにする。
-
すべての人に健康と福祉を:病気やけがから守られる社会をつくる。
-
質の高い教育をみんなに:すべての子どもが学校に通えるようにする。
-
ジェンダー平等を実現しよう:性別による差別をなくす。
-
安全な水とトイレを世界中に:きれいな水をすべての人に届ける。
-
エネルギーをみんなに そしてクリーンに:再生可能エネルギーを広める。
-
働きがいも経済成長も:良い仕事を増やし、経済を発展させる。
-
産業と技術革新の基盤を作ろう:持続可能な社会を支える仕組みを作る。
-
人や国の不平等をなくそう:経済格差を減らす。
-
住み続けられるまちづくりを:災害に強い街をつくる。
-
つくる責任 つかう責任:資源を無駄にせず大切に使う。
-
気候変動に具体的な対策を:地球温暖化を防ぐ行動を起こす。
-
海の豊かさを守ろう:海を汚さず、海の生態系を守る。
-
陸の豊かさも守ろう:森林や土地を守り、多様な生物を保護する。
-
平和と公正をすべての人に:暴力や差別のない社会を実現する。
-
パートナーシップで目標を達成しよう:国際協力で目標を実現する。
これらはどれも重要な目標で、相互に関係しています。
特に、小学生の皆さんには「海の豊かさを守ろう」など、身近に感じられる目標から取り組むことをおすすめします。
SDGs14「海の豊かさを守ろう」の意味と目的
SDGsの目標14「海の豊かさを守ろう」は、海洋環境を保護し、持続可能に利用することを目的としています。
海は地球の表面積の70%を占め、私たちの生活に欠かせない役割を果たしています。

海洋生物は食料として重要であり、気候を安定させる働きもあります。
ですが、海洋プラスチックごみや過剰漁業などの問題が深刻化しており、このままでは2050年には海にあるプラスチックの量が魚より多くなるとさえ言われています。
こうした状況を改善するため、世界中で取り組みが進められています。
この目標では、プラスチックごみを減らすことや、持続可能な漁業を推進すること、そして海洋酸性化を防ぐための取り組みが含まれています。
海を守ることは地球を守ることにつながるため、私たち一人ひとりの行動が非常に大切です。
日本のSDGs14における現状と課題
日本は四方を海に囲まれた島国であり、海の恩恵を大いに受けていますが、課題も多く抱えています。
特に、使い捨てプラスチックの廃棄量では、アメリカに次いで世界で2位とされています。
この膨大な量のプラスチックごみが海に流れ込み、環境問題を引き起こしているのです。
また、日本のスーパーやコンビニでは、商品が過剰包装されていることが一般的です。
そのため、まずは私たちが日常生活の中でプラスチックの使用を減らす努力が必要です。
さらに、漁業においても乱獲を防ぐためのルールが求められています。
日本が海の豊かさを守るためには、政策だけでなく、一人ひとりの意識と行動が重要です。
SDGs14で今問題になっていること
SDGs目標14「海の豊かさを守ろう」では、海洋環境における多くの問題が取り上げられています。
その中でも、特に深刻な問題として以下の4つが挙げられます。
- 海洋プラスチックごみ
現在、世界の海には1億5,000万トン以上のプラスチックごみが存在するとされ、毎年800万トンが新たに流入しています。このペースが続けば、2050年には海のプラスチック量が魚の量を上回ると言われています。 - 海洋酸性化
化石燃料の使用による二酸化炭素の増加が原因で、海水が酸性に傾きつつあります。これにより、サンゴ礁の死滅や貝殻が形成されにくくなるなど、生態系に深刻な影響を及ぼしています。 - 乱獲と違法漁業
魚を取りすぎる「乱獲」やルールを無視した違法漁業は、海洋生物の数を急速に減少させています。一部の魚種は絶滅の危機に瀕しており、これが漁業や食糧供給に直接的な影響を与えています。 - 海洋生態系の破壊
開発や汚染による沿岸部の破壊が進み、生物が住みにくい環境が増えています。これにより、漁業や観光業が支えられている小規模な島嶼国や沿岸地域の経済にも悪影響が出ています。
これらの問題は、SDGs14の目標を達成するために早急な対応が必要です。
一人ひとりが環境への影響を考えた行動を取ることが求められています。
海のゴミ問題とは?私たちにどんな影響がある?
海のゴミ問題は、海に捨てられたり流れ込んだゴミが、海洋環境や私たちの生活に深刻な影響を与えることを指します。
この問題は主に以下のような影響を及ぼします。
1. 海洋生物への影響
海洋ゴミの約80%はプラスチックで、これが海洋生物にとって大きな脅威となっています。例えば、ウミガメや海鳥はプラスチックをエサと間違えて食べてしまい、消化器官が詰まることで死んでしまうことがあります。また、網やロープなどのゴミに絡まって動けなくなり、命を落とす生物も少なくありません。
2. 食物連鎖への影響
プラスチックが細かく砕けた「マイクロプラスチック」が海洋生物の体内に取り込まれると、その有害物質が魚を通じて私たちの体内に蓄積される可能性があります。これにより、人間の健康にも影響が及ぶことが懸念されています。
3. 漁業や観光業への影響
海がゴミで汚染されると、水産資源が減少し、漁業が成り立たなくなります。また、観光地としての魅力が失われることで、観光業にも打撃を与えます。これらは地域経済にとって深刻な問題です。
4. 環境の美観の損失
海岸や川辺に大量のゴミが漂着すると、自然の美しさが損なわれます。これにより、私たちが自然を楽しむ機会が減少するだけでなく、地元の住民にとっても精神的な負担となります。
このように、海のゴミ問題は私たちの日常生活にも直接的な影響を与えるため、一人ひとりがごみの削減や正しい廃棄方法に取り組む必要があります。
魚がプラスチックを食べるとどうなるか?
海洋プラスチックごみの中でも、特に問題視されているのが「マイクロプラスチック」です。

これは、プラスチックが自然環境で劣化して細かく砕けたもので、5ミリ以下の非常に小さな粒子です。
このマイクロプラスチックを魚が食べてしまうと、次のような影響があります。
1. 魚の健康への影響
マイクロプラスチックを摂取した魚の消化器官は傷つけられ、正常にエサを消化できなくなります。また、体内に取り込まれたプラスチックの有害物質が、魚の成長や繁殖能力を低下させることも分かっています。
2. 食物連鎖への影響
魚が取り込んだプラスチックやその有害物質は、食物連鎖を通じて上位の捕食者に移行します。最終的に、その魚を食べる人間にも有害物質が蓄積される可能性があり、健康リスクが高まります。
3. 水産業への打撃
プラスチックを摂取した魚は商品価値が下がるため、水産業にとって大きな損失となります。また、魚の健康が損なわれることで、漁獲量が減少するリスクもあります。
4. 生態系のバランスの崩壊
プラスチックごみが生態系全体に影響を及ぼすことで、海洋生物の多様性が失われる危険性があります。これにより、海の食物連鎖のバランスが崩れ、他の生物にも悪影響が及びます。
魚がプラスチックを食べる問題は、私たちの食生活や健康に直結しているため、決して他人事ではありません。
私たち一人ひとりがゴミの削減やリサイクルに取り組むことで、この問題の解決に貢献できるのです。
SDGs14「海の豊かさを守ろう」で私たちや小学生でもできることは?
海洋汚染の対策として私たちにできること
海洋汚染の問題を解決するためには、私たち一人ひとりの行動が重要です。

特に、日常生活でできる以下の取り組みが効果的です。
1. プラスチックの使用を減らす
海洋ゴミの約80%がプラスチックであるため、使用量を減らすことが汚染対策の第一歩です。例えば、買い物時にマイバッグを使う、飲み物を持ち歩く際にはマイボトルを活用することで、使い捨てプラスチックを減らせます。また、ストローや使い捨てスプーンを避け、再利用可能なものを選ぶことも大切です。
2. ゴミを正しく分別しリサイクルする
ゴミを捨てる際には分別を徹底し、リサイクルに適した形で廃棄することが重要です。例えば、ペットボトルは飲み残しを洗い流してからリサイクルボックスに入れることで、資源として再利用されやすくなります。
3. ゴミ拾い活動への参加
海岸や川で行われるゴミ拾い活動に参加することで、実際に海洋汚染の現状を目の当たりにできます。これにより、自分が海を守る一員であることを実感し、環境意識を高めることができます。
4. 環境に優しい商品を選ぶ
日常生活の中で、環境に配慮した商品を選ぶことも効果的です。例えば、環境に優しい固形シャンプーや再利用可能な食品容器を使うことが推奨されます。また、海洋プラスチックを材料とした商品を購入することで、リサイクルを支援できます。
5. 排水への配慮
家庭で大量の洗剤や油を直接排水口に流さないようにすることも、間接的に海洋汚染を防ぐ一助となります。これらの物質が河川や海に流れ込むと、生態系に悪影響を及ぼす可能性があるためです。
これらの行動を積み重ねることで、海洋汚染の進行を食い止めることができます。
特に、小学生の皆さんには、身近なところから始めることが重要です。
SDGs14で自分たちにできることとは?
SDGs14の目標を達成するために、私たちができることは多岐にわたります。
小学生でも取り組みやすい具体例を以下にまとめました。
1. マイバッグやマイボトルの利用
レジ袋やペットボトルの使用を減らすために、マイバッグやマイボトルを持ち歩く習慣をつけましょう。これにより、使い捨てプラスチックの使用量を大幅に減らすことができます。
2. エコラベル付きの商品を選ぶ
スーパーや市場で魚を買うときは、MSC(海のエコラベル)やASCラベルの付いた商品を選びましょう。これらは、持続可能な漁業や適切な養殖場で生産されたことを示す認証マークです。
3. ゴミ拾いイベントへの参加
海岸や河川で行われる清掃イベントに家族や友達と参加してみましょう。楽しく取り組めるだけでなく、海を汚すゴミの現状を知るきっかけにもなります。
4. 情報を広める
SNSなどを活用して、ゴミ拾いや環境保護活動について発信することも、SDGs14の達成に貢献する一つの方法です。他の人にも海洋問題への関心を広げることができます。
5. 学校での取り組み
学校で環境問題について学び、友達と一緒にアイデアを出し合うことも大切です。例えば、環境に優しい学用品を使ったり、校外学習でゴミ拾いを企画したりすることが考えられます。
6. リサイクル意識の向上
ペットボトルや缶などの資源ゴミを正しく分別することが、小学生でもすぐにできる貢献です。また、学校や地域で行われるリサイクル活動に参加するのも良いでしょう。
小さな行動でも、多くの人が協力すれば大きな変化を生み出します。
SDGs14の目標は、私たち全員の努力によって達成されるものです。
小学生も取り組める「3つのR」とは?ごみを減らす工夫
「3つのR」とは、
Reduce(リデュース)、Reuse(リユース)、Recycle(リサイクル)のことです。
これは、ゴミを減らし、環境を守るための基本的な考え方です。

小学生も取り組みやすい具体的な方法を紹介します。
1. Reduce(リデュース):ごみを減らす
日常生活でごみを減らす行動がリデュースに当たります。たとえば、買い物時にマイバッグを使ってレジ袋をもらわない、使い捨てのカトラリーを使わず自分のものを持参するなどが挙げられます。また、必要以上に物を買わない習慣をつけることも大切です。
2. Reuse(リユース):繰り返し使う
プラスチック製品や衣類を捨てずに何度も使用することがリユースの一例です。たとえば、使わなくなった文房具を友達に譲ったり、古い衣類をリメイクして新しいものにすることもできます。
3. Recycle(リサイクル):資源として再利用する
家庭や学校で出るゴミを正しく分別し、リサイクル可能なものを資源として再利用する行動です。特に、ペットボトルや缶を分別して出すことは小学生でも簡単にできる取り組みです。
この「3つのR」を意識して生活することで、私たちが出すゴミの量を減らし、海洋汚染を防ぐ大きな一歩を踏み出すことができます。
海岸のゴミ拾いでできることとその効果
海岸のゴミ拾いは、環境保護の観点から非常に効果的な行動です。
小学生を含むすべての人が簡単に参加できるこの活動は、海洋汚染を防ぎ、自然環境を守る重要な役割を果たします。
ゴミ拾いでできる具体的なこと
- 海に流れ込むゴミを防ぐ
雨や風によって海に運ばれる前に、海岸に落ちているゴミを拾うことで、海洋プラスチック問題の拡大を防ぎます。これにより、海洋生物がゴミを誤って食べることや絡まることを減らすことができます。 - 環境問題への理解を深める
実際にゴミ拾いをすることで、どのような種類のゴミが捨てられているかを知ることができます。特にペットボトルやプラスチック製品の多さに気づくと、日常生活での使い方を見直すきっかけになります。 - 地域社会への貢献
ゴミ拾いは地域の環境を美しく保つだけでなく、観光客や住民が安心して利用できる場所を作ります。また、海岸の美しさを保つことで地域の魅力も向上します。
ゴミ拾いの効果
- 環境への即効的な改善:拾ったゴミが海に流れるのを防ぎ、海洋汚染を減らします。
- 生態系の保護:ゴミが減ることで、海洋生物が安心して生息できる環境が保たれます。
- 社会的な意識改革:ゴミ拾いを通じて、多くの人が環境問題を考え直すきっかけを得ることができます。
特に小学生にとっては、ゴミ拾いは楽しい学びの機会となり、環境問題を実感する大切な体験となります。
マイボトルやエコバッグの活用でできる貢献
プラスチックごみ問題を解決するためには、日常生活で使い捨て製品を減らす努力が必要です。
その中でも、マイボトルやエコバッグの活用は、手軽で大きな効果をもたらします。
マイボトルの活用
- 使い捨てペットボトルを減らす
水筒やタンブラーを持ち歩くことで、ペットボトル飲料の購入を減らせます。例えば、1日1本のペットボトルを避けるだけで、年間約365本の削減になります。 - 環境負荷を軽減
ペットボトルはリサイクル可能ですが、実際には多くが適切に処理されず、海洋ごみとなっています。マイボトルを使うことで、これを防ぐことができます。 - 経済的メリット
ペットボトル飲料を購入するコストを削減できます。さらに、カフェなどではマイボトルを使うと割引が受けられる店舗も増えています。
エコバッグの活用
- レジ袋の削減
毎回の買い物でエコバッグを使用することで、使い捨てレジ袋の消費量を大幅に減らせます。例えば、週に3回買い物をする家庭なら、年間で約150枚のレジ袋を節約できます。 - 環境に優しい素材の選択
布製や再生可能素材で作られたエコバッグを選ぶことで、さらに環境への配慮ができます。
これらの取り組みは、小学生でも簡単に実践できるため、家族で取り組むのもおすすめです。
SDGs14で推奨される「エコラベル付き商品」を選ぼう
SDGs14の達成に向けて、持続可能な漁業や養殖場からの水産物を選ぶことが重要です。
その目印となるのが「エコラベル」です。
エコラベルの種類と意義
- MSCラベル(海のエコラベル)
MSCラベルは、乱獲を防ぎ、持続可能な漁業で獲られた魚介類に付けられる認証です。これにより、漁業資源が守られ、生態系のバランスが保たれます。 - ASCラベル
ASCラベルは、適切に管理された養殖場で生産された魚介類に付けられます。環境への影響を最小限に抑えた方法で育てられた水産物を選ぶことができます。
エコラベル商品を選ぶメリット
- 環境保護への貢献:乱獲や環境破壊を防ぐ活動を支援できます。
- 品質の保証:厳しい基準をクリアした商品であるため、安全性や品質が高いとされています。
スーパーや市場で買い物をする際には、これらのラベルを意識して選ぶことが、海の未来を守る行動につながります。
世界と日本のSDGs14取り組み事例を紹介
世界の取り組み
- バングラデシュのプラスチック袋禁止
バングラデシュでは、2002年に世界で初めてプラスチック袋を全面禁止しました。この政策により、ゴミの減少や水質改善が進んでいます。 - オランダの「The Ocean Cleanup」プロジェクト
オランダでは、海洋プラスチックごみを除去する革新的な装置を開発し、世界中の海でゴミ回収を行っています。
日本の取り組み
- レジ袋有料化
2020年から全国でレジ袋の有料化が始まり、使い捨てプラスチックの削減が進んでいます。 - 海ごみゼロウィーク
全国規模で実施されるゴミ拾いキャンペーンで、多くの地域住民が参加し、海洋ゴミ問題への意識を高めています。
これらの事例は、SDGs14を達成するための具体的なヒントとなります。
海洋プラスチック問題解決のためのアイデア集
海洋プラスチック問題は、SDGs14「海の豊かさを守ろう」において特に深刻な課題の一つです。

世界中の海には、すでに1億5,000万トン以上のプラスチックごみが存在し、毎年800万トンものプラスチックが新たに流れ込んでいると推定されています。
この問題を解決するためには、私たち一人ひとりが具体的な行動を起こすことが重要です。
以下は、実践可能なアイデアを集めたものです。
分別とリサイクルの徹底
正しい分別とリサイクルが海洋プラスチック削減の基本です。日常生活の中で、プラスチックごみを適切に分別し、リサイクル可能なものは資源として再利用する習慣をつけましょう。たとえば、ペットボトルはキャップとラベルを取り外し、リサイクル用の回収ボックスに入れることが重要です。日本ではプラスチックのリサイクル率は約85%に達しており、リサイクルシステムが発展していますが、家庭での分別意識がさらに高まることで、この数字をもっと向上させることができます。
さらに、食品容器や包装材についても、リサイクルの仕組みを理解し、分別ルールを守ることが求められます。地域ごとの分別ルールを家族で確認し、特に小学生向けにはゲーム感覚で分別を楽しむ方法も効果的です。
再利用可能な製品の利用
使い捨てプラスチック製品の消費を減らすために、再利用可能な製品を選ぶことも有効です。例えば、以下のような選択肢があります:
- ステンレス製のストロー:洗って何度も使えるため、使い捨てストローを避けることができます。
- 布製の食品ラップ:ミツロウを使用した布製ラップは、環境に優しく、長期間使用可能です。
- 再利用可能な飲料容器:マイボトルや保温マグカップは、使い捨てペットボトルの代替として便利です。
これらの製品を選ぶことで、家庭から出るプラスチックごみの量を大幅に減らすことが可能です。特に小学生向けには、自分専用のエコグッズを持つことで環境意識を高めることができます。
教育と啓発
環境問題についての教育と啓発活動は、長期的な解決策として非常に重要です。学校や地域社会での取り組みを通じて、多くの人々に知識を広めることで、行動を促すことができます。
- 学校での教育:小学生向けの授業では、海洋プラスチック問題をテーマにしたワークショップや、ゴミのリサイクル方法を学ぶ実践的なプログラムを導入することが効果的です。例えば、SDGs14に関連する絵本や教材を活用し、子どもたちに「自分たちにできること」を考えさせる場を提供しましょう。
- 地域イベントの活用:地域で開催されるゴミ拾いや清掃活動に参加することで、実際の環境問題を肌で感じる機会を提供できます。さらに、清掃後に集めたゴミの種類や量を振り返り、問題の原因や解決策について話し合うことで、より深い理解が得られます。
- デジタル教育の活用:オンラインで環境問題を学べるコンテンツやゲームを利用することも効果的です。これにより、楽しく知識を深めることができます。
海洋プラスチック問題は一朝一夕では解決できませんが、私たち一人ひとりが「分別とリサイクル」「再利用可能な製品の選択」「教育と啓発」に取り組むことで、確実に改善できます。
特に、小学生がこうした行動を学び、実践することで、次世代のリーダーとして地球環境を守る役割を果たすことが期待されています。
SDGs14を達成するために、私たちができることを少しずつ実行していきましょう。
海の豊かさを守るための学校や家庭でできること
SDGs14「海の豊かさを守ろう」を実現するためには、学校と家庭が一丸となって取り組むことが重要です。
小学生向けにもわかりやすい方法で環境保護の意識を高めることは、次世代の地球を守る大きな一歩となります。
以下では、具体的な実践例を紹介します。
学校での取り組み
- 環境保護ポスターの作成
SDGsをテーマにしたポスターを子どもたちが作成し、校内や地域の掲示板に貼り出すことで、SDGs14への意識を広げることができます。たとえば、プラスチックごみ問題や海洋生物の保護に関するメッセージを描いたポスターを作ることで、自分たちにできることを考えるきっかけとなります。特に「海の豊かさを守ろう」というテーマで創作することで、SDGs14に特化した学びが深まります。 - ゴミ拾いイベントの実施
学校の行事として、地域の海岸や川辺でのゴミ拾い活動を企画することも効果的です。単なる清掃活動としてだけでなく、拾ったゴミを分類し、どのような種類のゴミが多いかを分析することで、環境問題の現状を体験的に学べます。また、イベントを通じて、SDGsや持続可能な社会の重要性について友達や家族と話し合う機会が生まれます。 - 環境学習プログラムの導入
授業でSDGs14をテーマにした特別学習を実施することも有効です。たとえば、海洋プラスチックの影響を分かりやすく解説する教材や、海の生態系を守るための取り組みを紹介する動画などを活用できます。こうした学びを通じて、「私たちにできること」を具体的に考え、行動に移せるようになります。
家庭での取り組み
- エコバッグやマイボトルの使用
家庭での買い物や外出時に、エコバッグやマイボトルを持ち歩く習慣を作ることが、海洋プラスチックごみの削減につながります。例えば、ペットボトル飲料を購入する代わりに、自宅で水やお茶を用意しマイボトルに入れるだけで、一家全体で年間数百本のペットボトル消費を削減することが可能です。 - 環境に優しい商品を選ぶ
日常的に使用する洗剤や食料品を選ぶ際には、環境に配慮した商品を選ぶよう心掛けましょう。たとえば、詰め替え可能な洗剤や再利用可能な食品保存容器を選ぶことで、プラスチックごみの発生を減らせます。また、海洋資源を守るためには、MSC(海のエコラベル)やASCラベルがついた魚介類を積極的に購入することも重要です。 - 家庭内でのゴミ分別の徹底
家庭で出るゴミをしっかりと分別し、リサイクル可能なものを正しく処理することで、ゴミの適切な処理が可能となります。子どもたちにゴミの分別方法を教えることで、環境問題への関心を家庭全体で共有することができます。
学校と家庭の連携の重要性
学校と家庭が連携してSDGs14に取り組むことで、子どもたちの環境意識はさらに高まります。たとえば、学校で学んだ内容を家庭で実践することで、行動が日常生活に根付くようになります。また、家庭での取り組みを学校で発表する機会を作れば、他の子どもたちにも良い影響を与えることができます。
具体的には、学校で学んだ「海洋プラスチックの問題」を家族で話し合い、休日に一緒にゴミ拾い活動を行うといった取り組みが考えられます。このような連携によって、地域全体にSDGs14への意識が広がり、持続可能な社会を作るための一歩となるのです。
ゴミ拾いイベントに参加するメリットとは?
SDGs14「海の豊かさを守ろう」を達成するためには、私たち一人ひとりの行動が欠かせません。
その中でも、ゴミ拾いイベントは、環境保護への意識を高めるだけでなく、地域社会にもさまざまなメリットをもたらす活動です。
特に小学生向けには、楽しみながら学び、行動に移すきっかけとなる重要な機会と言えます。
以下に、具体的なメリットを解説します。
地域環境の改善
ゴミ拾いイベントの最も直接的な効果は、地域環境が目に見えてきれいになることです。海岸や川辺、公園などでの清掃活動を通じて、プラスチックごみやペットボトル、ビニール袋などが回収され、自然環境の美しさが取り戻されます。
具体例として、日本のある海岸で行われた大規模な清掃活動では、たった1日で200キログラム以上のゴミが回収されました。このような結果は、地域の人々にとっても目に見える形での成果となり、環境への意識向上につながります。特に、小学生が自分たちの手でゴミを拾う体験をすることで、「私たちにできること」が具体的に感じられるようになります。
学びの場としての活用
ゴミ拾いは、環境問題について学ぶ絶好の機会でもあります。例えば、回収したゴミを分類し、その内容を分析することで、どのような種類のゴミが多いのかを知ることができます。プラスチック製品や使い捨て製品がどれほど多いかを目の当たりにすることで、私たちの日常生活が海洋汚染にどのように影響を与えているのかが具体的に理解できます。
さらに、ゴミ拾いイベント後にディスカッションを行うことで、「どうしてプラスチックごみが増えるのか」「海洋生物にどんな影響があるのか」といった疑問について考える時間を作ることができます。このような活動は、小学生向けにSDGs14の重要性をわかりやすく伝えるためにも非常に効果的です。
地域コミュニティとのつながり
ゴミ拾いイベントは、環境を守るという共通の目標を持つ人々が集まる場でもあります。例えば、家族や友達同士で参加するのはもちろん、地域の異なる世代の人々が一緒に活動することで、連帯感やコミュニティの絆が深まります。
特に、イベントを通じて新しい友達を作ったり、地域の課題を共有することで、環境問題への取り組みがより一層広がることが期待されます。また、参加者同士が知識やアイデアを共有することで、より効果的な解決策が生まれる可能性もあります。
プラスチックを減らす生活習慣でできること
SDGs14「海の豊かさを守ろう」を実現するためには、プラスチックごみの削減が欠かせません。
プラスチックは便利で広く使われていますが、使い捨て製品が海洋汚染の主要な原因となっています。
日々の生活でプラスチックを減らす行動を意識することで、地球規模の課題解決に貢献できます。
以下に、小学生でも実践できる具体的な方法をわかりやすく紹介します。
マイバッグを持ち歩く
日常の買い物でエコバッグを使うことは、レジ袋の使用を減らす最も簡単な方法です。例えば、日本ではレジ袋有料化が進んでおり、年間約400億枚使われていたレジ袋の消費量が大幅に削減されています。
具体的な効果
1人が毎回エコバッグを使うことで、年間100〜150枚のレジ袋を削減できると言われています。この行動が広がれば、プラスチックごみが海に流れ込む量を大幅に減らすことが可能です。さらに、小学生が家族にエコバッグの利用を提案することで、家庭全体の取り組みが強化されます。
マイボトルを使う
ペットボトルの代わりにマイボトルを持ち歩く習慣をつけることで、使い捨てプラスチックの使用を減らせます。例えば、1日1本ペットボトル飲料を買う代わりにマイボトルを使うと、1年間で約365本のペットボトルが節約できます。
具体的な活用方法
- 学校やスポーツ活動に水筒を持参する。
- 外出時にマイボトルを持ち歩き、カフェや飲食店で再利用可能な容器に飲み物を入れてもらう。
また、多くのカフェではマイボトルを利用すると割引を受けられる店舗もあり、経済的なメリットもあります。
使い捨て製品を避ける
プラスチック製のフォーク、スプーン、ストローなどの使い捨て製品を避けることも重要です。これらの製品は一度使用されるだけで廃棄され、適切に処理されなければ海に流れ込みます。
代替案
- 再利用可能なステンレス製のストローを使う。
- 食事の際には自分の箸やスプーンを持参する。
例えば、小学生が学校の遠足やピクニックに自分専用のカトラリーセットを持っていくことで、自然を守る意識が高まります。
プラスチック削減行動の効果
これらの生活習慣を取り入れることで、私たち一人ひとりが環境への負荷を減らすことができます。特に、小学生がこうした行動を実践することは、家庭や学校全体への影響力が大きく、持続可能な生活を広げるきっかけとなります。
具体的なデータ
ある調査では、1人が1年間で50本のペットボトルを節約するだけで、約13キログラムのCO2排出を削減できることが分かっています。このように、小さな行動が地球規模の問題解決に貢献する可能性を秘めています。
プラスチックを減らす行動は、小さな努力から始められます。
エコバッグを持つ、マイボトルを使う、自分の箸やスプーンを持参する、といった行動は簡単でありながら、SDGs14「海の豊かさを守ろう」の達成に大きく貢献します。
これらの習慣を家庭や学校で広げることで、「私たちにできること」をさらに強化していきましょう。
ここでは、SDGs14「海の豊かさを守ろう」について、小学生向けにわかりやすく、さらに「私たちにできること」を考えるための質問とその回答をまとめました。
SDGs14って何のこと?
SDGs14は「海の豊かさを守ろう」という目標で、海や海洋資源を守りながら使うことを目指しています。例えば、海洋プラスチックごみの削減、乱獲の防止、海洋酸性化の対策などが含まれています。小学生向けには、ゴミを減らして海の生き物を守る取り組みをわかりやすく学ぶことから始めるのがおすすめです。
SDGs14は小学生でも何かできるの?
はい、もちろんです!SDGs14では「海の豊かさを守ろう」という目標が掲げられていますが、小学生が取り組めることもたくさんあります。たとえば、ゴミを正しく捨てることや、エコバッグやマイボトルを使うことが簡単にできる行動です。これらは海に流れ込むプラスチックごみを減らすのに役立ちます。
海のプラスチックごみはなぜ問題なの?
プラスチックごみは、海の生き物にとって大きな危険です。たとえば、ウミガメがビニール袋をエサと間違えて食べたり、海鳥がプラスチックを飲み込んでしまうことがあります。さらに、プラスチックが分解されると「マイクロプラスチック」になり、魚を通じて私たちの体内に入る可能性もあります。
学校でできるSDGs14の活動は?
学校でできる活動としては、ゴミ拾いイベントや環境ポスター作りがあります。たとえば、海のゴミ問題をテーマにしたポスターを作り、校内に展示することで、みんなの意識を高めることができます。また、地域の川や公園でゴミ拾いをすることで、実際に環境を良くする取り組みができます。
海洋ゴミを減らすために私たちができる一番簡単なことは?
一番簡単で効果的な方法は、エコバッグやマイボトルを持ち歩くことです。使い捨てプラスチック製品を避けるだけで、私たちの生活が海洋ゴミに与える影響を減らすことができます。小学生向けには、自分専用のマイバッグや水筒を持つことを習慣にするのがおすすめです。
海の豊かさを守るために買い物で気をつけることは?
スーパーで魚を買うときには、MSCラベルやASCラベルが付いた商品を選ぶことが推奨されます。これらは持続可能な漁業や養殖場で生産されたことを示すラベルで、乱獲を防ぐ取り組みに貢献できます。
SDGs14に関する授業ってどんな内容なの?
SDGs14の授業では、海洋ゴミや海洋酸性化、乱獲の問題などを学びます。さらに、「私たちにできること」として、ゴミの削減や環境に優しい生活習慣について考える時間が設けられています。小学生が実践できる具体例を挙げることで、行動に結びつけやすい内容になっています。
小学生が家でできることって何?
家でできることとして、ゴミの分別や環境に優しい製品の選択があります。たとえば、リサイクル可能なペットボトルや紙製品を使うことで、プラスチックの使用を減らせます。また、使い捨てスプーンを避けて、自分専用のカトラリーを使うことも効果的です。
「海の豊かさを守ろう」が実現したらどうなるの?
SDGs14が達成されると、海の中で暮らす生き物たちが安全に暮らせる環境が整います。また、きれいな海が観光や漁業を支えることで、地域経済にも良い影響を与えます。これにより、私たちの未来がより明るく、持続可能なものになります。
海を守る行動を始めたいけど、何から始めればいい?
まずは、小さなことから始めてみましょう。エコバッグを使う、マイボトルを持つ、家族でゴミ拾いをするなど、身近な行動がSDGs14に貢献します。さらに、学校や家庭で「海の豊かさを守ろう」という目標について話し合い、みんなで取り組むことが大切です。
【小学生向け】SDGs14とは?私たちにできることをわかりやすく解説!のまとめ
最後にこの記事のポイントをまとめました。
【あわせて読みたい関連記事】

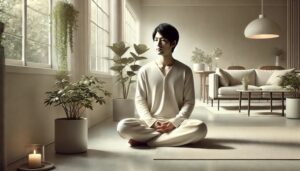
【本記事の関連ハッシュタグ】

